

これでまるわかり!増税で影響が出る業種の現状とは?
消費税の引き上げは家計にとって大きな痛手です。増税の影響は家庭だけにとどまらず、ビジネスの現場でも「コスト上昇」として重くのしかかってきます。では、具体的にどのような業種がどれほど影響を受けるのでしょうか?その実情をわかりやすく整理します。
Tax Increase増税で変わる働く現場のリアル
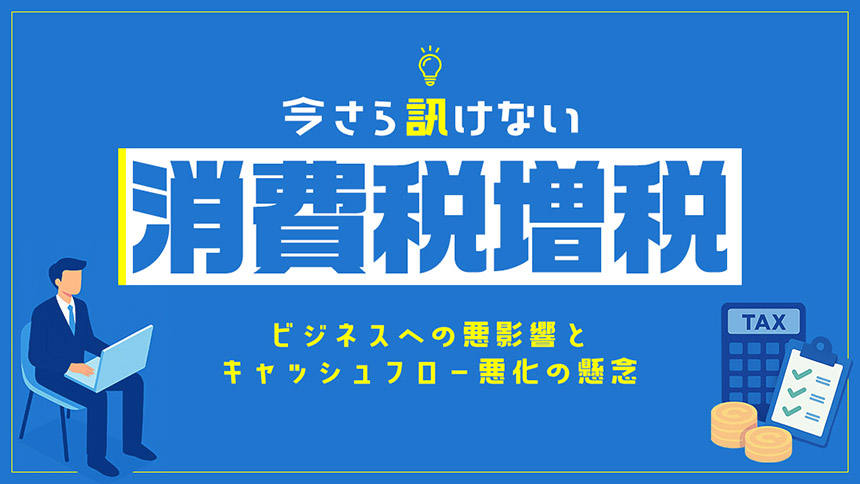
2019年10月1日、消費税が8%から10%に引き上げられました。
(※食品など一部は軽減税率8%を維持)
家庭の負担増に注目が集まるなか、見過ごされがちなのが職場への影響です。
業務用の備品や仕入れコストが上がるだけでなく、軽減税率の区分によって現場が混乱するケースも出てきています。
増税の影響が顕著な業種として小売業が挙げられます。
商品を直接消費者へ販売するという性質上、税負担がダイレクトにのしかかってきます。
ただ、その他業種には無関係かといえばそんなことはありません。全てのビジネスにおいて負担増は起きています。
消費税増税がどう影響しているのか、具体的に見ていきましょう。
増税がビジネスにもたらす影響
消費税10%への引き上げは、企業にとって「コスト増加」と「売上停滞」の二重苦をもたらします。
特に中小企業や消費者向け業種では、値上げによる客離れと、据え置きによる利益圧迫の板挟みが深刻です。
商品の販売価格の上昇
消費税の引き上げは、販売価格に直結する小売業にとって大きな打撃になります。
特に家電、家具、アパレル、日用品など、高単価またはまとめ買いが多い商品を扱う業界への影響は深刻です。
客離れや買い控えが起きる
たとえば、10万円の家電を購入した場合、8%時代は税込108,000円だったものが、10%では110,000円に。
たった2%の違いでも、金額としては2,000円の上昇。
この「割高感」「値上げ感」は消費者の購買意欲に大きく影響し、「今は買わないでおこう」という買い控えにつながります。
特に収入が限られている家庭や高齢者層にとっては、2%の違いでも購入判断を左右する大きな要因になります。
売上は増えても利益が減る?

価格を転嫁できず、税込価格を据え置きにする企業も少なくありません。
その場合、増税分を企業側が負担する形となり、「実質的な値下げ」となってしまいます。
売上はキープできても、利益率が大きく低下することは避けられません。
小規模店ほど影響が大きい
大手と違って価格交渉力の低い中小企業や個人商店では、仕入れコストの上昇を吸収する余力が乏しいのが現実。
その結果、値下げ競争や特売頼みの悪循環に陥りやすく、体力勝負の消耗戦に追い込まれます。
仕入れコストの上昇が経営を直撃
増税の影響は販売価格だけではありません。
製造業・サービス業を含むあらゆる業種が、仕入れコストの上昇という現実と向き合っています。
原材料費、備品費、消耗品費などあらゆる経費が増加すれば、当然、利益率は圧迫されます。
「軽減税率」は混乱の火種?
さらに複雑さを加えているのが「軽減税率制度」です。
たとえば、
| 菓子類・飲料水(会社の備品) | 軽減税率(8%) |
|---|---|
| ケータリング | 標準税率(10%) |
| 会議・打ち合わせの飲食物 | 持ち帰りか社内飲食かで税率が変わる |
このように、同じ「食品」でも用途や提供方法によって税率が変わるため、経理や総務の現場では判断に迷うシーンが出るでしょう。
帳簿処理・請求書の確認・仕訳入力など、管理コストと作業時間が大幅に増加しています。
また、文房具や清掃用品などの備品は軽減税率の対象外で10%が適用されるため、日々の業務に不可欠な出費ほどジワジワ効いてきます。
値上げしにくい業種のジレンマ
特に厳しいのが、価格をすぐに反映できない業種です。
- 公共インフラ関連
- 長期契約が前提のBtoB取引
- 官公庁・自治体と契約する業務 など
これらの業種では、契約期間中に価格改定を行うことが難しく、増税分を企業が丸ごと吸収する形になることも。
その結果、内部コストの削減や業務効率化が急務となり、現場は一層の負担を強いられることになります。
増税の影響が大きい業種とは?

消費税の引き上げは幅広い業界に影響を与えますが、中でも以下の3つの要素を抱える業種は、特に大きなダメージを受けやすくなります。
- 仕入れコストの増加
- 商品価格への影響
- 軽減税対象・対象外商品を同時に扱う
この3点を軸に、どの業界がどんな苦労を抱えているのかを見ていきましょう。
小売業界
スーパー、コンビニ、専門店などの小売業は、仕入れコストの上昇・価格転嫁の難しさ・軽減税率の複雑さという三重苦に直面しています。

たとえば、家電や家具を扱う専門店では、仕入れコストと販売価格の上昇が直撃。
スーパーやコンビニでは、食品と生活用品が混在し、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の線引きに追われます。
さらに、おまけ付きお菓子や酒類、医薬品など、税率の適用に専門的知識が必要な商品も多く、売り手も買い手も混乱しがちです。
結果として、価格戦略に頭を悩ませながら、現場の対応工数も増えるという負のスパイラルが生じています。
農林水産業界
農業・漁業・畜産などの一次産業では、何をどう使うかによって税率が変わるという軽減税率の制度が、実務上大きな壁になります。
| 「人の食用」として出荷 | 軽減税率(8%) |
|---|---|
| 「家畜用」として販売 | 標準税率(10%) |
このように、商品自体は同じでも、“用途”の違いだけで税率が変わるのです。
しかも、「人の食用として売ったものを家畜の餌に使った場合」は、形式上は8%でOKという例外も。
こうしたグレーな判断を都度迫られることになり、ただでさえ人手不足が深刻な現場にさらなる混乱をもたらしています。
製造業
製造業全体で見れば、適用税率はおおむね10%ですが、食品を扱う製造業では話が別です。
| 食品本体 | 軽減税率(8%) |
|---|---|
| 梱包材やラベル、資材 | 標準税率(10%) |
| 添加物 | 食用か工業用かで税率が異なる |
つまり、一つの商品をつくる工程で複数の税率が絡むのです。
そのたびに仕訳・帳簿管理が複雑になり、税率ミスや請求書の食い違いが発生しやすくなります。
製造業における工程と会計の分離が進んでいない企業では、この対応が後手に回り、経理処理の混乱やキャッシュフローのズレにもつながりかねません。
軽減税率という制度は、価格を据え置きながら一部の負担を軽減する狙いがありましたが、実際の現場では「どちらの税率を適用すべきか」の判断が最大の負担となっています。
増税は単なる数字の問題ではなく、「運用と現場負担」の問題でもあるのです。
増税による資金繰り悪化
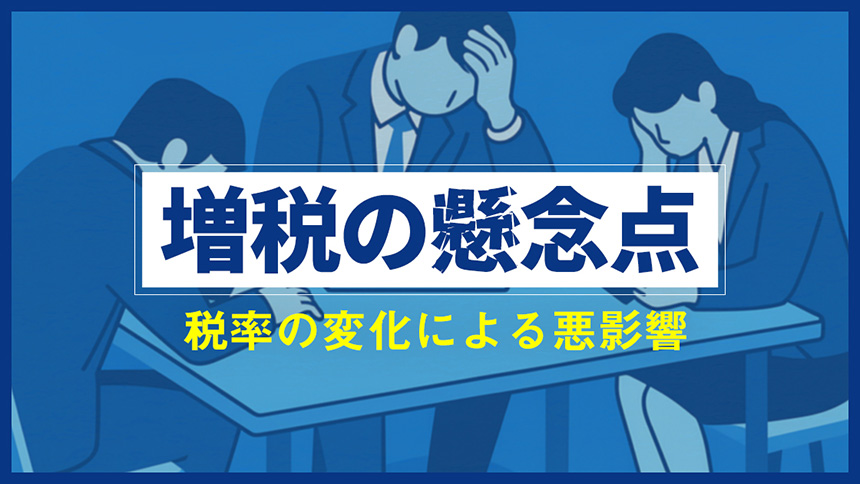
2019年10月1日、消費税が10%に引き上げられました。
しかし、前月までに受けた注文や請求については、原則として旧税率(8%)が適用されます。
つまり、売上は8%で計上されるのに、仕入れや経費は10%で発生するという税率ギャップが一時的に発生したのです。
とくに以下のようなケースが影響を受けやすくなります。
| 9月末に納品 | 従来の税率による売上(8%) |
|---|---|
| 10月に仕入れ | 増税後税率による仕入(10%) |
このようなタイムラグにより、「入ってくるお金は少ないのに、出ていくお金は多い」という状況が発生。
日々の運転資金に余裕がない中小企業や、利幅の小さい卸売業・飲食業では、この2%の差が思いのほか大きな負担となります。
増税という制度変更は、単に「価格が上がる」という話ではありません。
現場では、資金繰り、事務処理、価格戦略など、多方面にわたる影響が日々の業務にのしかかっています。
一過性の制度変更で終わらせず、継続的な運用のサポートと、現場に即した制度設計が今こそ求められています。
売掛金売却によるキャッシュフロー改善
消費税増税のように一時的、かつ解決の目処が立っている状態であれば、売掛金(請求書)を売却して支払日を待たずに現金を手に入れるという方法も有効です。
いわゆる「ファクタリング」というサービスです。(ファクタリングについて詳しくは「5分で理解するファクタリング活用術」を参照ください)
ファクタリングは融資に比べて割高な調達コストである反面、債権の売買行為なため審査という概念はなくスピーディーな取引が可能です。
買取に掛かる手数料は増税差分の2%を超えるため、できれば利用せずに耐えたいところですが、どうしてもキャッシュが足りない!という状況でしたらファクタリングも視野にいれて対策を練ってみてはいかがでしょうか。